旧法借地権とは、1992年8月1日より前に設定された借地権で、借地人(土地を借りる人)を強力に保護するという特徴があります。
建物の構造により存続期間が異なり(堅固建物30年以上、非堅固建物20年以上)、更新拒絶が極めて困難なため、実質的に半永久的な土地利用が可能ともいわれるこの権利。今も、多くの物件に設定されています。
メリットが多い権利ではありますが、住宅ローンが組みにくく、売却時には地主の承諾と譲渡承諾料(売却価格の約10%)が必要になるなどのデメリットも…。
この記事では、そんな旧法借地権について、そして新法との違いについて深堀りしていきます。
借地権についてお困りの場合は、専門業者が初回無料で対応します。オンラインの場合60分まで、LINEやメールの場合は5往復まで無料でご相談可能です。
旧法借地権が今も存在する理由は?

旧法借地権とは、1992年8月1日に借地借家法(新法)が施行される前の「借地法」に基づいて設定された借地権のことです。
旧法借地権は「建物を所有する目的で地主から土地を借りる権利」であり、戦後の住宅不足という社会背景から、借地人の生活を守ることを最優先に設計されています。
旧法借地権の最大の特徴は、地主が更新を拒絶することが非常に困難な点です。借地人が更新を希望し、建物が現存している限り、地主側に「正当な事由」がなければ契約は自動的に更新されます。この正当事由の要件は非常に厳格で、地主が単に「土地を使いたい」という理由だけでは認められません。
現在でも多くの旧法借地権が存在する理由は、日本の法律における「法改正の不遡及の原則」にあります。
新法が施行されても、すでに存在していた借地契約には旧法が引き続き適用され、契約を何度更新しても旧法の権利が継続されるわけです。その結果、借地人にとって極めて有利な条件での借地契約が、現在も維持されています。
建物の種類で異なる存続期間の仕組み
旧法借地権では、建物を「堅固建物」と「非堅固建物」に分類し、それぞれ異なる存続期間を定めています。この分類は新法にはない旧法独特の制度です。
堅固建物とは、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)など、耐久性の高い建物を指します。一方、非堅固建物は木造や軽量鉄骨造など、比較的耐久性の低い建物が該当します。この区別により、以下のような期間設定となっています。
堅固建物の場合
- 当初の最低存続期間:30年以上
- 期間の定めがない場合:60年
- 更新後の期間:30年
非堅固建物の場合
- 当初の最低存続期間:20年以上
- 期間の定めがない場合:30年
- 更新後の期間:20年
契約書で定められた期間がこれらの最低期間より短い場合、その約定は無効となり、法定の最低期間が自動的に適用されます。この仕組みにより、借地人の長期的な居住の安定が保証されています。
旧法借地権と新法の5つの重要な違い

存続期間と更新制度の大きな差
1992年8月1日に施行された借地借家法(新法)は、地主と借地人の権利バランスを見直すために制定されました。旧法借地権と新法の普通借地権には、以下の5つの重要な違いがあります。
1. 建物構造による区別の有無
旧法では建物の堅固性により存続期間が異なりますが、新法の普通借地権では建物構造に関係なく一律30年以上となりました。この変更により、契約条件がシンプルになった一方で、非堅固建物の借地人にとっては最低期間が10年延長されることになりました。
2. 更新後の期間設定
更新期間において、旧法と新法では大きな差があります。旧法では何度更新しても堅固建物30年、非堅固建物20年という長期間が維持されます。しかし新法では、初回更新が20年、2回目以降は10年と段階的に短縮されます。この違いは、借地権の長期的な安定性において決定的な差となっています。
3. 正当事由と立退料の明確化
地主が更新を拒絶する際の「正当事由」について、新法では判断要素がより明確化されました。旧法では正当事由の内容が曖昧だったため、地主と借地人の間で紛争が絶えませんでした。新法では、地主と借地人双方の土地使用の必要性、土地の利用状況、契約の経緯に加え、「財産上の給付」(立退料)も考慮要素として明記されています。
4. 建物滅失・再築時の取り扱い
建物が火災や災害で滅失した場合の再築について、旧法では地主が遅滞なく異議を述べなければ借地期間が延長される仕組みでした。一方、新法では建物滅失後の再築時に地主が異議を述べた場合、借地権が消滅する可能性があり、地主の意向がより反映されやすくなっています。
5. 更新拒絶要件の厳格さ
旧法借地権の最大の特徴は、地主による更新拒絶が極めて困難な点です。新法では「定期借地権」という更新のない借地権が導入され、地主が将来的に土地を確実に回収できる選択肢が生まれました。しかし旧法にはこのような制度はなく、地主は常に強固な正当事由を立証しなければならないため、事実上の半永久的な権利となっています。
建物朽廃時のリスクと対策
旧法借地権において特に注意すべきは、建物の朽廃(きゅうはい)による権利消滅のリスクです。朽廃とは、建物が老朽化により通常の居住や利用が不可能になった状態を指します。
契約で存続期間を定めていない場合、建物が朽廃すると借地権自体が消滅してしまいます。これは期間が長い代わりに、建物の老朽化で権利が終了するという仕組みです。特に木造などの非堅固建物は朽廃しやすいため、期間の定めがない契約では大きなリスクとなります。
一方、契約書に明確な存続期間が記載されている場合は、期間中に建物が朽廃しても借地権は残存期間中は消滅しません。このため、契約内容の確認は借地権を保有する上で極めて重要です。
旧法借地権付き物件のメリット・デメリット

購入価格の安さと居住の安定性がメリット
旧法借地権付き物件の最大のメリットは、購入価格の安さです。土地の所有権が付いていないため、周辺の土地付き一戸建てや所有権マンションと比較して、相場の60〜80%程度で購入できます。特に地価の高い都心部では、この価格差が顕著に現れ、初期投資を大幅に抑えることが可能です。
もう一つの大きなメリットは、借地人の権利が極めて強く、長期居住に有利な点です。前述のとおり、旧法借地権は地主による更新拒絶が非常に困難であるため、一度契約が成立すれば半永久的にその土地に居住できます。これは居住の安定性を重視する人にとって、所有権物件にも劣らない安心感を提供します。
さらに、多くの旧法契約では地代が長期間見直されていないケースが多く、月々の地代が固定資産税・都市計画税の合計額より安価な場合もあります。このような物件では、長期的なランニングコストを抑えられる可能性があります。
住宅ローンの難しさと各種承諾料がデメリット
一方で、旧法借地権付き物件には重大なデメリットも存在します。最大の問題は、住宅ローンが非常に組みにくいことです。
金融機関は土地の所有権がない借地権付き建物を担保として評価しにくく、また売却時に地主の承諾が必要なため流動性が低いと判断します。融資を受けるには、地主に金融機関への担保提供を承諾してもらう必要があり、これには別途承諾料が発生することもあります。結果として、現金購入を前提とせざるを得ないケースが多くなります。
また、毎月の地代負担も無視できません。地代は経済情勢の変化や地価上昇により値上げを請求される可能性が常にあります。さらに、借地権の更新時には更新料として更地価格の3〜5%程度(数百万円単位)を支払う必要があり、数十年に一度とはいえ大きな負担となります。
建て替えや売却時には必ず地主の承諾が必要で、それぞれ承諾料が発生します。建て替え時は更地価格の3〜5%、売却時は借地権価格の10%程度が相場とされています。これらの承諾料や手続きの煩雑さが、旧法借地権付き物件の流動性を大きく低下させる要因となっています。
旧法借地権の相続・売却時の重要ポイント
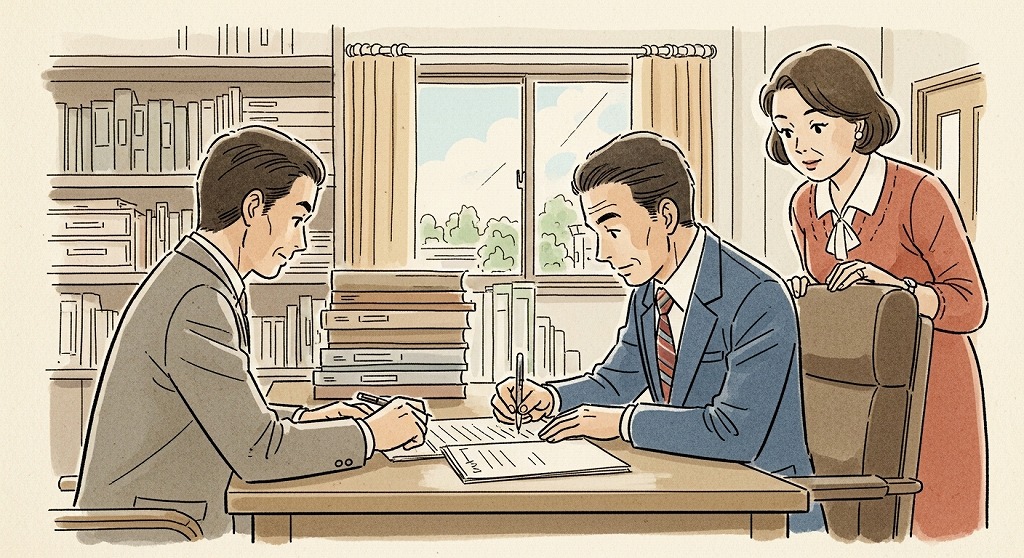
相続時の名義変更は法的に承諾不要
借地権者が亡くなり、法定相続人が権利を承継する場合、これは民法上の「賃借権の譲渡または転貸」には該当しません。相続は法律上の地位の包括的な承継であるため、地主の承諾は法的に不要です。
しかし実務上は、地主側が契約関係を明確にするための「名義変更手続き」を求め、その際に「名義変更料」や「名義書換料」という名目で金銭を請求してくる慣習があります。この名義変更料は売却時の譲渡承諾料とは法的性質が異なり、あくまで事務手続き費用として扱われるべきものです。
高額な請求をされた場合は、法的には承諾が不要である点を理解し、低額での交渉に持ち込むことが重要です。無用な支払いを避けるためにも、相続の際には借地権専門の不動産会社や弁護士に相談することを強く推奨します。
売却時は承諾料10%が相場
借地権を第三者に売却する場合、地主の承諾は法律上必須です。地主の承諾なしに売却しても、地主は契約解除を主張できるため、事実上、承諾なしの売却は不可能です。
承諾を得る際に支払う譲渡承諾料の相場は、借地権価格(売却価格)の10%程度とされています。例えば、3,000万円で借地権を売却する場合、300万円程度の承諾料が必要になります。この10%という数字は、旧法借地権の流動性の低さを定量化したコストと捉えることができます(ただしエリア・習慣により異なる場合もあります)。
地主が合理的な理由なく承諾を拒否した場合は、借地人は裁判所に「借地権譲渡の許可」を申し立てることができます。裁判所は通常、地主側の不利益を緩和するために、譲渡承諾料の支払いを条件として許可を出します。
相続税評価と税金対策
相続税や贈与税の課税対象となる借地権の価額は、国税庁が定める方法により「自用地の価額×借地権割合」で算出されます。借地権割合は路線価図に記載されており、地域により30〜90%まで設定されています。
例えば、自用地価額が2億円で借地権割合が70%の場合、借地権の相続税評価額は1億4,000万円となります。所有権(100%評価)と比較して評価額が低くなるため、相続税対策として有効に機能する場合があります。ただし、評価方法が複雑なため、正確な税務対策には税理士や不動産鑑定士による専門的な評価が不可欠です。
地代と更新料の適正相場を知る
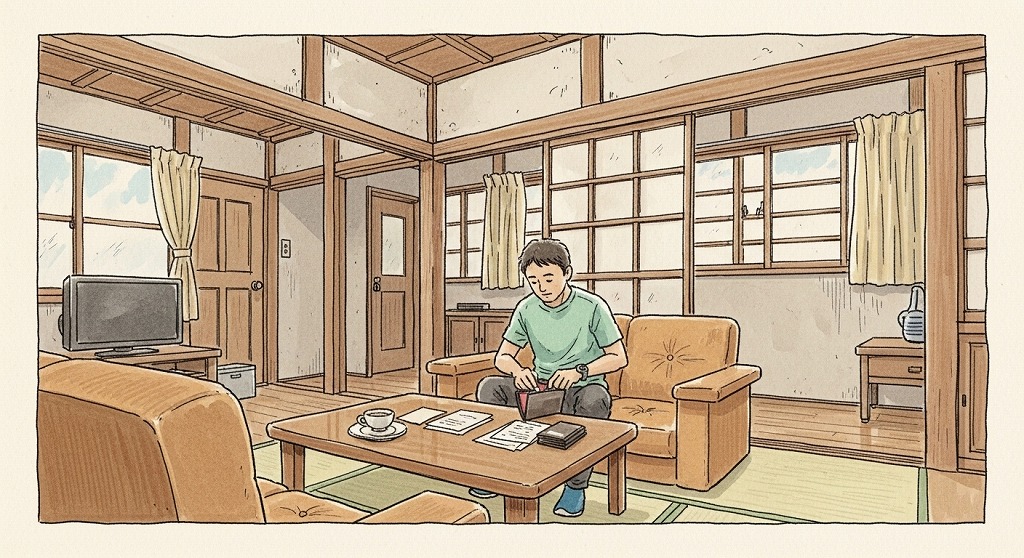
地代の適正価格は公租公課の3倍が目安
地主から地代の値上げ請求があった場合、適正額を判断する客観的な基準として「公租公課倍率法」が用いられます。公租公課とは、固定資産税や都市計画税など土地にかかる税金の総称です。
東京高裁の判例(昭和59年6月20日)では、地代の適正額について公租公課の約3倍程度を相当地代とする考え方が示されています。この基準は、地主からの不当な値上げ請求に対する借地人側の対抗策として非常に有効です。
例えば、年間の固定資産税・都市計画税の合計が30万円の土地であれば、年間地代90万円(月額7.5万円)程度が適正水準の目安となります。特に旧法物件では長期間地代の見直しが行われていないことが多いため、この基準を参考に適正な地代水準を判断することが重要です。
更新料は契約書の確認が最優先
借地権の更新料については、実は法的な支払い義務が明確にあるわけではありません。更新料は慣習として発展してきたもので、相場は一般的に更地価格の3〜5%前後とされています。首都圏などの地価が高い地域では、この割合が高くなる傾向があります。
更新料の交渉においては、まず契約書を確認し、更新料に関する明確な規定があるかを確認することが最優先です。契約書に記載がない場合、原則として支払いの義務はありません。ただし、過去に更新料を支払った実績がある場合は、当事者間で支払いの合意があったとみなされ、支払い義務が生じる可能性があります。
現在支払っている地代が公租公課倍率法に基づく適正価格より著しく高い場合は、更新料の減額交渉の材料として活用できます。地代と更新料のバランスを総合的に判断し、適正な負担水準を維持することが重要です。
地代値上げ請求への法的対処法
地主が地代の不当な値上げを請求し、従来の地代の受領を拒否した場合、借地人は「弁済供託」という法的手続きを利用できます。これは、借地人が適当と認める地代を法務局に供託することで、地主が受け取りを拒否しても賃料債務を履行したことになり、契約解除リスクを回避できる制度です。
地代の値上げ交渉は法的紛争に発展しやすいため、地主から値上げ請求を受けた場合は、まず公租公課倍率法に基づき適正額を算出し、交渉がまとまらない場合は速やかに弁護士などの専門家に相談することが最も安全な対処法です。
よくある質問と回答

Q. 旧法借地権は新法に切り替えるべきですか?
原則として、借地人にとって旧法借地権を新法に切り替えるメリットはほとんどありません。旧法は新法より更新期間が長く、借地人保護の要件が極めて強固だからです。
新法に切り替えると、2回目以降の更新期間が10年間に短縮されるなど、借地人の権利が弱くなります。現在の強固な権利を手放すことは推奨されません。ただし、地主との間で地代の大幅減額や承諾料の免除など、全体として借地人の利益になると判断できる条件で合意が得られる場合は、切り替えを検討する余地があります。
Q. 旧法借地権付きマンションの建て替えは可能ですか?
旧法借地権付きマンションは、区分所有者全員が土地の借地権を持っています。建て替えを行う場合、まず区分所有者全員の合意を得る必要があり、さらに土地の地主の承諾も必須となります。
権利関係が複雑である上に、地主の承諾を得るために高額な承諾料の支払いが必要となるため、合意形成が極めて難航し、建て替えが事実上不可能になるケースが多く見られます。老朽化した旧法借地権付きマンションを購入する際は、この建て替えリスクを重く評価する必要があります。
Q. 地主が変わった場合の旧法借地権への影響は?
地主が土地を売却し、新しい地主になったとしても、旧法借地権が消滅することはありません。借地権は土地に付随する強力な権利であり、新しい地主に対しても引き続き、旧法に基づく権利を主張することができます。
ただし、建て替えや売却を行う際の承諾手続きは、新しい地主に対して行う必要があり、承諾料の交渉や支払いは新しい地主との間で行うことになります。地主が変わることで交渉の難易度が変わる可能性はありますが、借地権自体の法的な位置づけは変わりません。
Q. 旧法借地権物件は投資用として適していますか?
旧法借地権付き物件は購入価格が安いため、賃貸に出した場合に高い利回りを期待できる可能性があります。しかし、投資用物件として見た場合、以下の大きなリスクがあります。
まず、投資ローンを組むことが極めて難しく、現金購入が前提となることが多いです。また、売却時には地主の承諾が必要で、譲渡承諾料として借地権価格の10%程度を支払う必要があります。流動性が低く、売却益を確保するための出口戦略が立てにくいのが実情です。
したがって、投資経験が豊富であり、長期保有を前提とし、地主との交渉や法律的なリスク管理に慣れている場合に限定して検討すべきです。一般的な投資家にとっては、権利関係のシンプルな所有権物件の方が安全性が高いといえます。
まとめ – 専門家への相談で安全な取引を

旧法借地権は、1992年以前の法律に基づく借地人にとって極めて有利な権利です。存続期間が長く(堅固建物30年/非堅固建物20年、期間不定の場合は60年/30年)、更新拒絶の要件が極めて厳しいため、更新を繰り返すことで土地の利用が半永久的に保証されます。
しかし、この権利の強さは建て替えや売却の自由度の低さという側面も持ち合わせています。特に、契約で期間の定めがない場合は、建物が朽廃した瞬間に権利が消滅するリスクもあるため、契約内容の確認は急務です。
旧法借地権付き物件は初期費用を抑えたい居住者にとって魅力的な選択肢ですが、住宅ローンの制約、毎月の地代、数十年に一度の更新料(更地価格の3〜5%)といった財務的な計画が不可欠です。
地主との交渉が必要となる場面が多く、地代の値上げ請求に対しては判例に基づく適正価格(公租公課の約3倍)を根拠に交渉し、必要に応じて弁済供託手続きを利用して権利を守る知識が必要です。
旧法借地権に関わる取引や管理は複雑な法的手続きを伴うため、トラブルを未然に防ぎ、権利と資産を守るためにも、借地権に特化した専門家への相談を強く推奨します。当社では、旧法借地権に関する無料相談を承っております。購入・売却・相続・地代交渉など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
東京、大阪、名古屋、沖縄であれば提携各社が無料でご相談にお答えします。しつこい営業もありませんから、安心してご利用ください。
